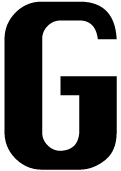INTERVIEW
自動運転と電動化の物流改革で築く“列島改造”
株式会社複合物流
代表取締役 筒井公平

物流の自動運転化と電動化によって、日本の産業・地域社会・環境課題を一挙に解決する壮大な構想が動き出している。株式会社複合物流の筒井公平代表は、深刻なドライバー不足やCO2排出といった課題を背景に、「物流新幹線」とも呼ぶ新たな物流インフラの構築に挑む。その構想の原点と、実現に向けた現場のリアルを語る。

「物流新幹線」という壮大な構想
私たちは、自動運転と電動化による物流改革を目指し、この構想を「物流新幹線」と呼んでいます。1964年の東京オリンピック前に東海道新幹線が誕生し、その後、山陽新幹線や東北新幹線が続いたように、今回は人ではなく物流のための幹線ネットワークを作るイメージです。現在、物流業界ではドライバー不足が深刻です。2030年には貨物の35〜36%が届かなくなるとも言われています。特に長距離便は厳しく、九州・首都圏間は1週間かかることもあり、この状況では若年層の参入が難しい。自動運転に変えれば、それを解消することができるのではないか、と考えています。加えて、ディーゼル車のCO2排出削減と幹線輸送の脱炭素化も重要です。東名阪の幹線輸送はCO2排出量が大きいため、EVや水素燃料電池トラックに切り替えることで大きな効果が期待できます。
さらに、次世代の自動運転と電動化で物流版新幹線ネットワークを作るだけでなく、私たちは田中角栄の列島改造論のように、それを活用した地方再生を実現したい、と考えています。日本全体の大動脈を活性化すれば、地方と首都圏の格差をなくすことができる。キーワードは、「物流版自動運転と脱炭素物流の新幹線ネットワーク」と「自動運転と電動化による列島改造」です。
インフラ構築の鍵となる高速道路直結型拠点整備
「物流版自動運転と脱炭素物流を実現する新幹線ネットワーク」において、必要なものは高速道路に直結した物流施設です。自動運転の大型トラックが市街地で走るのは危険が伴うため、これを基に「高速道路直結型物流施設」や「インターチェンジ直結型物流施設」という概念を作り出しました。おそらく当社が初めて打ち出したもので、現在では国交省や経産省でも使われています。この直結型物流施設では、高速道路上をシャトル便が往復。信号もなく安全であり、労働問題にも影響しません。水素燃料電池車や大型EVの充填・充電時間を1時間と見積もると、23時間の稼働が可能です。例えば、東京〜大阪間では生産性が従来比で最大4倍になります。
ただし、高速道路直結施設はエリアが非常に限られ、技術や法制度にもまだ課題があります。そこで、インターチェンジ直結化以外での自動運転の走行サポートも必要です。現在、インターチェンジから1km圏内の範囲も視野に入れ、地権者や行政と交渉を進めている段階です。これまでに、当社がコンサルした大手デベロッパー2社が京都・城陽市で進めている計画があり、早ければ2027年には完成予定です。しかし、東側の施設が未完成だとキャッチボールができません。将来的には、東名高速道路の実質的な起点である横浜町田IC周辺エリアや新東名の起点である厚木南IC周辺エリアが中心になると考えています。
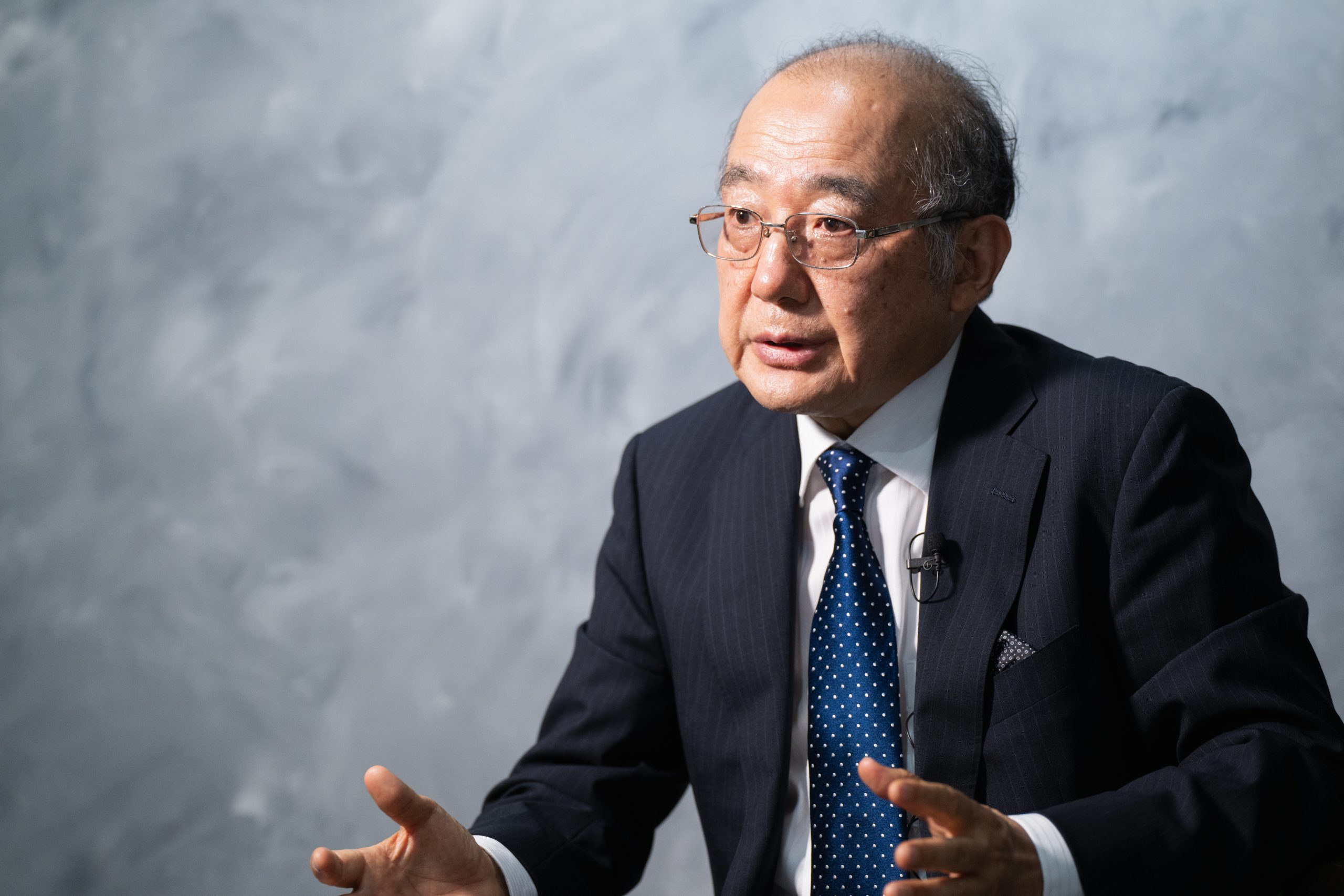
技術実証だけでなくそれをビジネスに
国が進める自動運転プロジェクトなどは、高速道路内で自動運転車両が技術的に走行できるかを確認する技術実証が中心です。しかし、我々は、技術実証はビジネス化に向けた一項目に過ぎないと考えています。新幹線車両ができてもターミナル駅がなければ意味がないように、自動運転のターミナルがなければ技術実証も無意味だと、10年ほど前から言い続けてきました。
インフラ整備は技術実証よりもはるかに大変です。我々は、技術実証だけではなく、自動運転の物流体系ができる構想全体、ビジネスがどうやって立ち上がって実際に稼働するかというところまで含めてビジネスモデルを構築しています。大動脈と域内配送を結節する物流施設を造ることによって貨物情報や様々なデータが集まり、物流デベロッパーにとっても最適な場所になるでしょう。さらに、自動運転車両の出入りや水素ステーション設置が進めば、環境問題の最先端施設としての価値も生まれます。デベロッパーにとっても「成功する仕組み」を最初から作っているのも特徴です。
地域を再生する物流を
自動運転と電動化による物流ネットワークが整備されれば、コスト削減と生産性向上がかない、田中角栄が提案した列島改造と同じような経済効果が期待できると考えています。長距離便のコストの半分は人件費です。現在、物流費が商品価格を上回ることもありますが、それも自動運転化により解消されるはずです。地方の新鮮な農産物が翌日には首都圏に届き、地方経済は首都圏の消費経済と直結し、活性化するでしょう。
さらに、海外への輸出も可能になります。現在は地方から首都圏の港に運ぶドライバーが足りませんが、自動化すればシャトル便でスムーズに輸送が可能になるはずです。農産物だけでなく、工業製品や工芸品もコンテナで運び、コンテナヤードから直接輸出手続きを進められる。これにより、地方物産品の輸出も促進されるのはないでしょうか。
自ら動くしかないという決意
自動運転物流のアイデアは、安倍政権時代の隊列走行の構想からヒントを得たものです。当時、当社は、神戸で行き詰まっていた日本初の高速道路直結型物流施設計画の相談を受け、行政やインフラ事業者との交渉を請け負っていました。一方で、当時から高速道路で自動運転車両が運行されるには、高速道路直結型の物流施設の整備が必須だと感じていました。そこで、自動運転と高速道路直結型物流施設とを新結合させればいいと思い立ったわけです。一方で、新幹線と同じように、まずは東京〜大阪間が重要で、そこから始めなければ意味がないと考えました。それが、今のプロジェクトにつながりました。
プロジェクトを進める中で、日本の官僚組織の縦割りの問題や、中央官庁と地方自治体の連携不足なども見えてきました。これらを解決するためには自分で動くしかないと感じ、地権者一人一人の説得から始めることになりました。国土交通大臣にも説明しましたが、最終的には地権者への説得なくして進まないことがわかり、他人任せにはできず、今も自ら動いています。
物流×農業の必要性
現在最も基本的な部分である地権者との交渉を行っていますが、これは非常に泥くさい仕事です。その過程で、農家の8割に後継者がいないという問題も浮き彫りになりました。これは全国の農家に共通する課題です。そこで、我々は農地を物流施設に転用する一方で、生産性の高い大規模ハウスを導入し、農業再生を図ろうとしています。
これを取り組まなければ、プロジェクトは進みません。国の高官たちが、この点を理解していないことも非常に大きな問題だと感じます。自動運転対応の物流施設には約50ヘクタールの土地が必要ですが、物流施設だけを作っても地域住民の理解は得られません。道の駅のような地域振興施設を設け、農地をつぶす代わりに生産性の高い農業を導入するというまちづくり全体を考える必要があります。これがなければ、行政の許認可や地権者・地域住民の同意は得られません。自動運転は農家・農業・まちづくりと一体となって進めるべきです。
日本の未来を形づくる“物流革命”
情報発信の面では、新聞への意見広告や出版活動を通じて構想の周知化を図っています。自動運転と脱炭素の物流改革を実現するには、技術だけでなく、インフラ、ビジネスモデル、行政交渉を含めた総合的アプローチが必要です。
この構想は、グローバルな自動車産業の生き残りと、日本国内の地方創生に貢献するものです。自動運転と電動化という世界的トレンドと地域経済再生というローカルな課題が交差する場所に、私たちの取り組みがあります。巨大な事業を立ち上げるには、全体を理解し、自ら発信し動くことが不可欠です。最も重要なのは地道な作業を続けること。それが物流革命を生み、次世代に誇れる未来を築くと信じています。