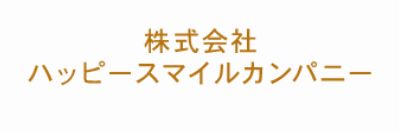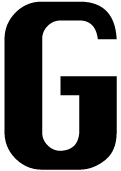INTERVIEW
予防歯科×食育で始まる“人育て”
株式会社ハッピースマイルカンパニー
代表 新井美紀

「歯が生えたら噛める」――誰もが抱くそんな思い込みを、長年の臨床と食育の現場から覆してきたのが、株式会社ハッピースマイルカンパニー代表・新井美紀さんだ。「授乳期からの経験によって、噛む力は育まれます」と語る新井さんが提唱するのは、手づかみ食べや味覚形成、自浄作用を軸にした「食育実践予防歯科」。子も親も健やかに育つ新しい“予防歯科×食育”の形とは。

「噛む力」を育むということ
私たちハッピースマイルカンパニーは、「噛む子を育む」をテーマに、子どもたちの健やかな成長を支える取り組みを行っています。事業の柱は3つ。歯科医院へのコンサルティング、専門職や乳幼児の保護者を対象としたセミナー・レッスン、そしてオリジナル商品の開発です。いずれも、私が歯科衛生士として培ってきた知見と、食育カフェで得た実体験をもとに、本当に役立つことだけを届けるようにしています。
私が重きを置いているのは、「噛む力は自然に身につくものではなく、経験の積み重ねによって育まれる」という考え方です。一般的には「歯が生えれば自然と噛めるようになる」と思われがちですが、これは大きな誤解です。発達のプロセスは、授乳期から離乳食期、幼児食期と、階段を上るように“積み上げ型”で、1つひとつの経験が次の段階を支えます。つまり、生後5か月でも6か月でも、これまでにどんな経験を積んできたかによって、口の動きや発達のスピードはまったく異なるのです。大切なのは、月齢よりも、「今この子が何をできるのか」「何がまだ難しいのか」を見極めること。その点、赤ちゃんは常に正直です。できることしかできませんし、無理をすれば「できない」というサインを出してくれます。保護者や指導者がそうした反応をその子自身の“答え”として受け止め、必要な支援を見極めていくことが、「噛む子を育む」第一歩であり、育児の根幹だと考えています。
食育カフェで見えた「噛む力」の原点
私は歯科衛生士として、長く子どもたちの予防歯科に携わってきました。そんな中、「むし歯予防の本質は食生活にある」と考え、2006年に食育情報を発信する「ママ・キッズカフェ」をオープン。当時は親子カフェが全国的に注目されていた時期で、地域に住む多くの親子と出会うことができました。子どもたちの食事の様子を見守る中で、私は大きな気づきを得ました。それは、歯が生えても上手に噛めない子どもたちがいるということ。そして、噛む力の出発点は、授乳期にあるということです。授乳のとき、赤ちゃんは舌や頬を使ってミルクを飲みます。その動きが咬筋を発達させ、次に迎える離乳期で噛む力へとつながるのです。ところが、授乳姿勢や方法によっては筋肉を十分に動かせず、必要な経験を積めないまま離乳期に入り、つまずいてしまうケースがあります。これは臨床の場だけでは気づけなかった大きな発見でした。
子どもの発達は本当に十人十色です。だからこそ私は、子どもが自らのペースで進められる「手づかみ食べ」を推奨しています。「さわりたい」「口に入れたい」という気持ちを尊重することで、子どもは試行錯誤を通じて口の動きを学び、保護者もその姿を観察する中で多くを学べます。親の役目とは、手を出しすぎず、離れすぎず、適度な距離で見守ること。まずは離乳食期に、子どもの様子を丁寧に観察する目を養ってほしいと思っています。

「はぐかむ®離乳食スプーン」に込めた想い
離乳食の介助をサポートする中で、市販のスプーンに使いづらさを感じ始めました。そこで、「赤ちゃんが食べやすい」「保護者が介助しやすい」「私たちが指導しやすい」──その3点を満たす商品として独自開発したのが「はぐかむ®離乳食スプーン」です。口に入る部分は極限まで薄くし、唇の力が弱い赤ちゃんでもしっかりと口を閉じられる仕様にしました。ボールの部分は平らかつ小ぶりに設計し、敢えて山盛りにすくえない構造にすることで、一口量を自然と最適化できるようにしました。保護者はつい一度に多く盛ろうとしがちですが、それでは赤ちゃんが食べ物を粉砕する前に飲み込んでしまい、噛む力の発達を妨げてしまいます。さらに柄はストレート型にし、上顎に離乳食を擦り付けるような誤った介助を防ぐ形状にしました。持つ位置にはハートマークのガイドを刻み、指を添える位置が一目でわかるデザイン。国産の木材を使い、女性職人が1本ずつ手作業で仕上げた温もりのあるスプーンです。
正しい介助方法が身につくのであれば、道具はなんでもかまいません。ただ、このスプーンは「どうすれば赤ちゃんが上手に食べられるのか」という15年もの試行錯誤の末、“誰が使っても正しい介助がしやすいという”再現性を追求した商品です。そのため、専門アドバイザーから介助方法を学んだ方のみ購入していただけます。「噛む力」を育むための知識とツールを共に届けることで、お子さんのペースで進む離乳期を少しでも楽しんでもらえたらという想いを形にしました。
「食育実践予防歯科」という観点
「予防歯科」というと、多くの方が歯みがきを思い浮かべると思います。しかし、食育カフェの運営で気づいたのは、「自浄作用が働く口を育てる」ことが虫歯予防にとって最も重要だということでした。噛むことで唾液を分泌させ、その唾液が食べかすや汚れを洗い流し、菌を住みつかせない環境をつくる。これが私の提唱する「食育実践予防歯科」です。その考えに確信が持てたのは、長年モニターとして関わってくれたお子さんたちのおかげです。中でも、生後まもなくから授乳姿勢や手づかみ食べなど発達に合わせた支援を行ってきた6歳の子は、乳歯が理想的な歯間スペースを保ちながら生え揃い、虫歯もなく良好な経過をたどっています。一方、同じ環境で育った兄姉は初期の支援が十分でなく、歯列に差が見られました。幼少期の“噛む経験”が、将来の口の形や健康に大きく影響することを実感した症例です。
また、自浄作用を促すには、噛む力だけでなく味覚を整えることも欠かせません。離乳期から味の濃いものに慣れると、甘い食品を求めやすくなり、口腔環境に悪影響を及ぼします。一方、味覚が整った子どもは必要以上に甘いものを欲さず、自然と菌の少ない状態が保てます。もちろん、歯みがきが不要というわけではありません。ただ、ブラッシングはあくまで“衛生管理の補助”であり、本来重要なのは、口が自らきれいに保てる力を育てること。その観点に立った予防歯科を、今後も実践していきたいと思います。
「噛む子」を育む、その先へ。
今後は、全国に「はぐかむ®離乳食スプーンアドバイザー」を誕生させ、離乳食介助指導やスプーン購入を誰もが行えるようにしていきたいと考えています。そして、単にスプーンの使い方を伝えるのではなく、離乳食を通じた親子の関係づくりや観察のポイントなど、より深い学びに繋げていきたいです。日本の離乳食は、栄養士を中心とした栄養バランス重視の指導が主流ですが、それだけでは子どもの発達を十分に支えられません。大切なのは、子どもが自ら選択し、考える力を育むこと。その最初のトレーニングが「手づかみ食べ」にあると私は考えます。産休や育休も取りやすい今の時代だからこそ、是非その時間を活用していただき、「噛む子」を育むための知識や環境づくり、ひいては “人育てカリキュラム”をお父さん、お母さんに届けていきたいです。さらには、噛む力の発達を促すお椀やおもちゃといったアイテム開発にも取り組みたいと考えています。
離乳食は単に「食べさせること」ではなく、“人を育てる入口”だと私は捉えています。そして、子どもの噛む力の発達を通じて、親自身も学び、変わり、育っていく。そんな循環を社会に拡げていくことが、子どもたちの幸せな未来への架け橋となればと願っています。