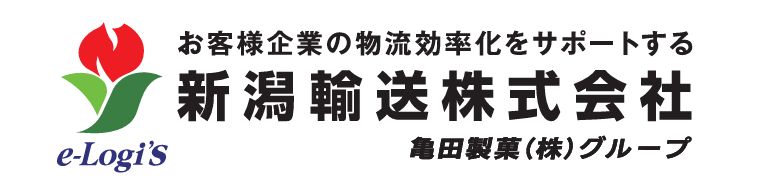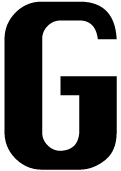INTERVIEW
“ありがとう”を運ぶ物流の未来。
新潟輸送株式会社
代表取締役社長 柴田俊雄

親会社・亀田製菓の物流を担うことから始まった新潟輸送株式会社。菓子を中心とした“共同配送”を軸に事業を拡大し、全国をカバーする配送ネットワークを築いてきた。亀田製菓での幅広い現場経験を背景に、品質向上と効率化の両立に取り組み続ける代表取締役の柴田俊雄さん。変化の激しい物流業界で、今どのような未来を見据えているのか──2030年に向けた構想を伺った。

菓子を軸に広がる共同配送ネットワーク
当社は1974年の創業以来、親会社である亀田製菓の輸送を担い、1980年以降は物流業務を本格的に展開してきました。事業の柱は、菓子を中心とした共同配送です。亀田製菓の物流を核に、他のメーカー様の商品も同じトラックに積み合わせることで効率的かつ安定した輸送を実現。さらに、拠点間を結ぶ幹線輸送事業や卸向けの物流センター事業も展開しています。本社を置く新潟に加え、埼玉・名古屋・京都に拠点を構え、それ以外の地域は協力会社様との連携により、全国規模の配送ネットワークを築いています。
現在、事業用倉庫は合計で約1万6,000坪を有し、繁忙期には外部倉庫も活用することで需要変動に対応しています。保有する車両は213台、フォークリフトは225台。関東エリアの所沢拠点では4t・10t車両が平常時で1日70台前後、繁忙期には110〜120台稼働しています。こうした体制をもとに、物流品質と安全を重視しながら、荷主様や社会の多様なニーズに応えることが当社の使命です。
三者の対話が支える物流基盤
私は亀田製菓で営業や開発を経験したのち、新潟輸送に出向してきました。その経緯から、物流の立場にいながらも卸様と直接話をできる環境があります。メーカー・卸・物流の三者が同じテーブルで課題を共有し合えることは、当社ならではの特徴です。
たとえば「2024年問題」や、運送事業法・物流効率化法の改正といった業界全体に関わるテーマについて卸様と協議し、メーカー様へフィードバックする。このように三者で問題を共有できることは、よりよい物流体制を築く上で大きなメリットです。さらに、ドライバーの労働環境改善や配送リードタイムの見直しといった現場レベルの課題も、三者で情報を突き合わせながら最適解を探ることができます。メーカー単独でも卸単独でも拾いきれない声を橋渡しし、効率や品質を高め、お客様の満足度向上につなげる。こうした“回路”を持てるのは、私が亀田製菓時代から培った多くの経験と人との出会いが礎になっているからです。物流は単独では完結しません。だからこそ、対話を通じて築かれた信頼関係こそが、当社の財産であり、強みです。この体制が共同配送を安定的に支え、当社ならではの競争力へつながっていると考えています。

効率と安全を両立する現場力
物流の品質を高めるには、現場の仕組みを自ら工夫し、改善し続けることが欠かせません。当社ではWMS(倉庫管理システム)や動態管理システムを導入し、現場に即した形で活用しています。大手物流企業に比べれば規模は小さいかもしれませんが、着実に積載率を高め、効率的な配送へとつなげています。さらに拠点再編による効率化も進めており、名古屋では従来600坪と1,000坪に分かれていた倉庫を統合し、2,000坪の施設へ移転しました。よりスムーズなオペレーションを実現する上で、拠点は常に見直すべき対象だと考えています。
効率化と並んで、物流に絶対的に欠かせないのが安全です。当社は「安全品質部」を設け、各事業所を巡回しながら日々の運行や作業手順を確認。他社の先進的な取り組みも積極的に学び、良いものは自社に取り入れる姿勢を徹底しています。一見地道にも見えますが、効率と安全を両立させる取り組みを絶えず改善し続けること、それが配送品質の安定や現場の負担軽減、ひいてはお客様の信頼に直結すると捉えています。
顧客と従業員の双方を守るために
私が大切にしているのは「お客様」と「従業員」、その両方です。どちらも事業にとっては不可欠であり、一方の満足だけでは企業は成り立たないからです。かつて営業時代の私は、「お客様に満足して頂くことこそ、企業の使命」と信じ、顧客満足の一点に注力してきました。しかし経営の立場になって痛感したのは、従業員の存在の大切さです。特に物流業は自動化が難しく、人材不足は利益に直結するシビアな課題。だからこそ、従業員が安心して働ける環境づくりがいっそう求められます。当社では「収入が低く残業が多い」という物流のイメージを払拭すべく、賃金体系や休日制度を改善し、「残業ありき」でない働き方を推進。国土交通省の「働きやすい職場認証制度」二つ星も取得しました。将来的には1日3~4時間だけでも勤務できる短時間ドライバーの制度を整え、女性や子育て世代にも働きやすい環境をつくりたいと考えています。
一方で、メーカー様の商品値上げに対し、物流費は同率で値上げされないという厳しい現実もあります。さらにトータルの物量が減少したことで、物流業界は多大なダメージを負っているのです。従業員が安心して働ける環境を整えつつ、持続的な成長を目指すためには、この厳しい現実を荷主様に粘り強く伝え、理解を得ることも不可欠だと思います。
拡張するネットワーク、進化する物流モデル
物流業の発展とは「ネットワークの拡張」と言っても過言ではありません。どのようなネットワークを築くかが物流品質に大きく影響します。当社はこれまで新潟から関東への輸送に強みを持ってきましたが、近年は所沢(埼玉)から名古屋・静岡への「横持ち輸送」に着手し、東名阪という大動脈に車両が入る体制を整えつつあります。また、輸送効率を高める施策として「ダブル連結トラック」も導入しました。25メートルの車両長で、2台分の物量を運べるこのトラックは、国土交通省より推奨され、人手不足への一手として業界からも注目を集めている輸送モデルです。導入には規制やコストなどの課題もありましたが、現在は順調に稼働しており、当社の発展を後押ししてくれるものと期待しています。
近年は国の実証実験に参加するなど、防災分野にも取り組んでいます。南海トラフ地震を想定した「日本海ルートBCP実証」では、新潟拠点を活かし、太平洋側の交通網の代わりに関西と関東を結ぶ実験を行いました。非常時に物流インフラを支えることは当社の社会的責任であり、行政主導の施策への参画は、企業としての存在感向上にもつながると考えています。
2030年へ、広がる物流の未来
2023年には、2030年を見据えた中期経営計画を策定しました。これは部長層が中心となって構築し、経営陣も議論を重ねて磨き上げてきたものです。私はこの計画を着実に実行していくことこそ、次世代への布石になると捉えています。まず重要なのは、国内輸配送の持続可能性をどう確保するかです。特に北陸、中・四国、九州といった地方では、人口減少の影響で輸送がますます難しくなっています。国や自治体と連携し、配送頻度やリードタイムを見直すことで、効率を維持しながら「消滅エリア」を生まないよう取り組んでいく必要があります。
一方で、親会社の亀田製菓は北米や東南アジアで海外展開を進めています。私たち新潟輸送としても、いずれはその海外ネットワークを支えられる存在にならなければなりません。そこでまず現状の課題を乗り越え、国内の配送体制をしっかりと確立した上で、海外物流への挑戦を視野に入れていきたいと考えています。ローカルを守りながら、グローバルに広がる産業を支える。その両輪を回すことで「グローカル」な物流の形を実現できるはずです。物流は社会を支えるインフラであり、“当たり前の日常”を支える仕事です。誰かの「ありがとう」のために、私たちはこれからも変化に対応し、縦横無尽に動き続けていきます。