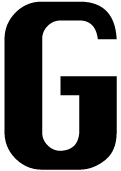INTERVIEW
人と地球をつなぐ“お下がり”の力
株式会社OSAGARI
IT統括 COO 小田拓夢、環境保全部・統括部長 上林大翼

左:IT統括 COO 小田拓夢 右:環境保全部・統括部長 上林大翼
不要になったモノを循環させ、社員の暮らしと環境を同時に支える福利厚生サービス「OSAGARI」。福利厚生でありながら、環境保全や社内コミュニケーションの活性化、子育て世帯の負担軽減など、効果実感度の高い仕組みとして高く評価されている。今回は、開発と営業の現場を担うお二人に話を聞き、「システムをどう設計するか」「どう広げ、社会に届けるか」というそれぞれの視点に迫った。

「お下がり」の文化を社内で
小田:私はシステム開発部門の統括として、福利厚生サービス「OSAGARI」の開発・運用を担当しています。このサービスは、不要になったものを“お下がり”として社員同士が譲り合えるというもの。たとえば、もう使わなくなったベビーカーや子供服を譲りたい人と、それらを必要とする人を社内でマッチングし、やり取りができるようになっています。一言で言えば、社内版のフリマアプリのようなイメージです。
現在は約100社に導入され、ユーザー数は4,000人近く。利用者からは「部署や拠点を越えた交流のきっかけになった」「譲った服を着たお子さんの写真を見られて嬉しい」といった感想をいただいています。社内コミュニケーションが盛んになることで、結果的に「離職率の低下につながっている」という声も。さらに「OSAGARI」の最大のメリットは、不要品の再利用によってCO₂排出削減に貢献できる点です。つまり導入すること自体が、社会課題であるカーボンニュートラルへの取り組みに直結するということ。その意味では「環境保全を推進している会社」として、企業のイメージ向上につながるという一面もあります。

「気持ちよく使える」仕組みをつくる
現在チームは8名体制で、管理4名と開発・運用を兼任する4名を中心に進め、必要に応じて外部エンジニアとも連携しています。「OSAGARI」自体は、複雑なシステムではありません。それよりも私が重視しているのは、とにかく“気持ちよく使えること”。どんなに立派な理念があっても、アプリの動作が遅かったりエラーが頻発すれば、ユーザーはすぐに「これじゃなくてもいい」と離れてしまいます。だからこそ、まずはシステムの安定性とやり取りの速度を最優先に考えてきました。加えて、写真を複数掲載できる仕様や、投稿テンプレートの実装、お互いの予定を合わせやすい画面設計など、社内での受け渡しが気軽に、スムーズに進められるような仕組みを整えています。
導入後は私やエンジニアが企業を訪問し、使用感や不具合の有無などを直接ヒアリングしていきます。「OSAGARI」が福利厚生として導入される以上、経営者が感じる価値とユーザーが感じる価値はしばしば異なります。だからこそ両者に届く設計を常に意識し、社内に生まれる良い循環を止めないよう、地道に磨き続けているのです。
「水族館」という夢が導くキャリアと展望
私はもともとNTTグループでエンジニアをしていました。大学時代からプログラミングに携わり、副業で教える仕事もしていたのですが、転機となったのは代表である五十嵐との出会いです。飲み会で初めて会ったときから、その行動力と発想力に強く惹かれ、数年後に「一緒にやらないか」と声をかけられた際は、転職を即決。私たちは「水族館をつくる」というゴールを定め、その実現のためにIT事業を本格的にスタートさせました。水族館とは一見突拍子もない構想に聞こえるかもしれませんが、これは「シャチを飼いたい」という五十嵐の夢から派生したもので、動物好きな私もその想いに賛同した結果生まれた目標です。現在はITビジネスで培った資金や仕組みを活かし、環境保全や動物保護を安定的に支えていくことが会社全体のビジョンになっています。
今後は、経営者層に環境問題の重要性を伝え、将来的には発展途上国への展開を通じてアパレル廃棄の削減に貢献したいと考えています。一方で「OSAGARI」を地域密着型の仕組みへと広げることで、地方都市の企業や住民をつなぎ、町おこしや定住促進に役立てたいという構想もあります。「IT×環境保全」のように、本来であれば交わらないと思われていた要素を自由な発想で掛け合わせることによって、当社の仕事のやりがいや楽しさは、よりいっそう広がっていくはずです。
営業現場から見た「OSAGARI」の価値
上林:私は環境保全部門の統括部長として、「OSAGARI」の営業活動とリサイクル事業を兼任しています。リサイクル事業とは、衣料廃棄物をバングラデシュの工場で繊維に戻し、掃除道具の材料として日本に再輸入するというもの。アパレル業界で発生する廃棄物は膨大で、その焼却処分によるCO₂排出は深刻な課題です。弊社では環境保全事業の一環として、こうしたリユース活動にも取り組んでいます。
「OSAGARI」をご提案した際、まず聞かれるのは「こんな福利厚生はじめて」という驚きの声です。従来になかった取り組みを提供できることに誇りを感じますし、子育て世代からは「洋服代の負担が減った」「パパ同士の交流が生まれた」といった感想をいただき、日々の励みになっています。営業の現場で感じるのは、“社員の暮らし”や“環境への取り組み”に積極的な企業ほど、導入を即決されやすいということです。福利厚生が形骸化しがちな中で、「OSAGARI」は環境保全や社内交流の促進という点で“実感度が高い仕組み”として高評価を得ています。さらに、少子高齢化や物価高が進む今、子育て世帯の負担を軽減するソリューションとしての一面もあり、営業活動ではその点も意識してアプローチしています。
“思う/思われる”が生む循環
突然ですが、私の夢は「シャチを飼うこと」と「世界196か国を制覇すること」です。その夢を叶える適職として選んだのがエンジニアでしたが、新卒時代には営業成績で全国1位を獲得したこともあり、今はその経験を活かして仕事に向き合っています。代表の五十嵐と出会ったときの感想は「自分と夢がまったく同じ人」。海外志向や「シャチを飼いたい」という夢まで一緒で、人柄にも強く惹かれ、一緒に働くことを決めました。不要品を循環させる仕組みは、環境負荷の軽減や動物愛護につながりますし、社員旅行で多くの国を訪れるなど、今は自分の夢と自然にリンクする日々を送っています。
私が仕事で大切にしているのは、“思う/思われる”という関係性です。「人はひとりではなかなか力を発揮できない」というのが私の考えで、私自身、五十嵐をはじめ、多くの人とのつながりの中で可能性を広げてきました。だからこそ、誰かを思い、また誰かから思われる――その循環が人と人をつなぐ価値の根幹だと考えています。「OSAGARI」を広げることは、まさにそんな循環を企業の中に浸透させるきっかけになります。同サービスは、単なる福利厚生ではなく、“思う/思われる”を社会全体に広げていく挑戦と言えるかもしれません。
“お下がり”を社会インフラへ
私は「OSAGARI」を社会に広げると同時に、社内の関係性や文化の構築にも力を入れています。その象徴の一つが社員旅行です。行き先は海外が多く、直近ではハワイ、次回は韓国やメキシコを予定。異文化や絶景に触れる体験は社員の視野を広げ、「次の旅行のために頑張ろう」というモチベーションにもつながっています。また、新卒時代に学んだ「人生設計研修」を会社でも導入しました。私は当時の研修で大谷翔平選手の恩師・佐々木監督にお会いしたことがあり、その経験を活かすため、マンダラチャートを用いた人生設計を社員にも実践してもらっています。夢や目標を持ちづらい時代ですが、私自身が「シャチを飼う」「世界196か国制覇」と掲げることで、社員も大きな夢を語ったり、互いに刺激を与え合えていることが嬉しいです。
今後は、バングラデシュの提携工場での衣料廃棄物リサイクルを継続し、環境保全活動をさらに推進していきます。また、10年後には「OSAGARI」の2,000社導入を達成し、“お下がりの連鎖”を地域に根付かせると共に、社会インフラへと発展させていくことが私たちの目標です。環境にも人にも優しく、誰もが安心して暮らせる社会。そんな未来を、「お下がり」とともに築いていきます。