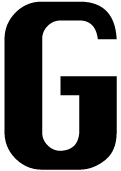INTERVIEW
「安心」に、最短でたどり着く小児科
たけのこキッズくりにっく
院長 塩見和之

患者の通院ストレスに着目し、スピーディな診察や待ち時間の削減など、数々の工夫を重ねる「たけのこキッズくりにっく」。診療とサービスの両面で「声なき声」に応え続けるその姿勢が信頼を集め、開業からわずか1年で月2,000人が来院するクリニックへと成長した。その根底にあるのは、「子どもの1日は大人よりもずっと重い」という塩見院長の価値観だ。子どものかけがえのない時間、そして家族の安心を守る取り組みに迫った。

「安心をより早く」届ける小児科クリニック
たけのこキッズくりにっくは、大阪府堺市・初芝駅前にある小児科・アレルギー科のクリニックです。「安心をより早く」をモットーに、小児患者とその保護者が抱える不安をいち早く和らげることを大切にしています。そのためには病気の診断だけでなく、「今どういう状態か」「今後どんな経過が予想されるか」「再診の目安は何か」といった見通しを丁寧に伝えることが、小児科医の責務だと考えています。
私自身、幼い頃からアレルギー体質で、小児科医との距離が近い環境で育ちました。だからこそ、小児科医としてのあるべき姿や理想の医療には人一倍こだわりがあります。医学部在学中から「町のお医者さん」として地域に貢献したいと考え、2024年5月に当院を開院しました。クリニック名の「たけのこ」には、竹の子のようにまっすぐ、健やかに育ってほしいという想いを込めています。また、竹の子が一気に成長するように、子どもの成長も一瞬。だからこそ、その貴重な時間に寄り添える存在でありたいと考えています。
快適な医療体験を追求する
診察に伴う患者さんのストレスを少しでも減らすため、当院では開業当初から4つの工夫を取り入れてきました。
1つ目は診察券のアプリ化です。紙の診察券は忘れがちですが、実際は保険証さえあれば診察は可能です。ならば診察券自体をなくし、患者さんの負担を減らしたいと考えました。2つ目は、時間枠での予約制です。順番予約制で「5番目」と言われても来院のタイミングが読めませんが、「15時に来れば受診できる」という明確な時間指定があれば、予定も立てやすくなります。3つ目はオンライン会計です。「診察は待てても、会計は待てない」という患者さんは多く、受付と会計を受け持つスタッフの負担も大きくなりがちでした。そこで、事前にクレジットカードを登録いただき、診察室で処方箋を渡した時点で会計を完了する仕組みを整えました。4つ目はオンライン診療です。継続処方など来院不要の場合には、オンラインで対応することで患者さんの手間を最小限に抑えるよう配慮しています。こうした仕組みづくりは一見ただの「効率化」に見えるかもしれませんが、本質は「少しでも早く安心を届けたい」という想いです。患者さんがスムーズに医療へアクセスできるよう、これからもよりよい体験設計を模索していきたいと考えています。

多くの患者を救うための「早い」「正しい」診療
当院には月に2,000人以上の患者さんが来院されますが、どれほど混雑していても、診察までの待ち時間は20分程度にとどめています。それを可能にしているのが、短時間で本質を見極める診断力です。私は、患者さんが診察室に入ってきた瞬間の表情や呼吸の様子、問診票の内容から、おおよその方向性を即座に見立てます。咳、鼻、熱などの症状を分類し、あらかじめ用意してある「診断の型」に当てはめていくことで、正確でスピーディな診療を実現しているのです。
また、専門領域に偏りすぎず、レントゲンや所見を丁寧に確認しながら、フラットな視点で診断を行うことも大切にしています。「この症状にはこの薬」と決めつけるのではなく、「目の前の患者さんにとって最善か」を常に考えること。その上で、必要と判断した際には、抗生物質やステロイドも積極的に処方します。大切なのは薬の種類ではなく、適切なタイミングで適量を処方できるかどうかです。結果として、「風邪が早く治る」「他院では治らなかった症状が改善した」といった声をいただくことも少なくありません。わざわざ遠方から足を運んでくださる患者さんもおり、当院への信頼の証として大きな励みになっています。
サービス業としての医療とは
「医療はサービス業だ」というのが私の考えです。ですから、医学的に間違っていない限り、患者さんのニーズには最大限応えるべきだと思っています。その姿勢の根底にあるのが、当院の理念でもある「言葉にできない声を聞く」こと。これには、二つの意味があります。一つは、まだうまく話せない子どもたちの体のサインを丁寧に読み取ること。もう一つは、患者さんの立場に立って本当に適切な対応ができているかを見極めることです。科学的に正しくても、本人の意志や納得が置き去りでは、治療がうまくいかないこともあります。
ニーズに目を凝らせば、自然と「声なき声」は聞こえてくるものです。そしてそれは、診療行為にとどまらず、「病院に行って、帰る」という一連の体験にも反映されるべきだと私は考えます。当院が待ち時間の削減やオンライン対応に取り組んできたのも、そうした意識の延長にほかなりません。医療の質と診療体験の質は、本来切り離せないものなのです。
「断らない医療」の実践
私が小児科医として最も大切にしているのは、お子さんを一日でも早く集団生活に戻すことです。子どもの一日は、大人よりもずっと濃く、貴重です。かけがえのない時間を守るためにもできるだけ早く、必要な医療を届けることを心がけています。その思いは、通院が難しいご家庭への訪問診療にもつながっています。たとえば重度の障がいを抱えていたり、大型バギーの使用などにより外出が困難な家庭には、こちらからご自宅へ伺うのです。小児科クリニックにおける訪問診療はまだ一般的とはいえませんが、「行きたくても行けない家庭」は確かに存在します。ならば、医療サイドが柔軟に動くべきなのではないでしょうか。
「困っている人がいるのなら、できることは全部やる」。そんな考えが、私の根幹にあります。リスクや手間があったとしても、必要とされる場には応えたい。そして1人でも多くの患者さんを救いたい。そのシンプルな想いが、今の当院をかたちづくっているのだと思います。
医療の枠を越えて、子どもと地域の未来を支える
将来的には4つの拠点展開を構想しており、現在は2院目の準備を進めているところです。以前勤めていた泉南地域は、私が担当していた患者さんも多く、かつ小児科医が不足しているエリアでもあります。そこで「安心をより早く」届けられるクリニックをつくることが、次のステップです。同時に、医療の枠を越えて福祉分野にも挑戦したいと考えています。今は、医療的ケアが必要な子どもたちのための放課後等デイサービスを計画中で、年内のスタートを目指しています。さらに、発達障害やダウン症の子どもたちに向けた学習支援の場も計画中です。知的なハンディがあっても、練習すれば、できることは増えると私は信じています。だからこそ、「無理」と決めつけずに、挑戦の機会を提供したい。それは必ず子どもたちの生きる力になり、そして親御さんの安心にもつながるはずです。
福祉は「慈善事業」の印象が強いですが、善意だけでは決して続けていけません。だからこそ私のような医療人が関与し、経営基盤を安定させることで、現場の人たちがやりがいを持って働ける環境をつくりたいと考えています。待遇が整えば、支援の質も向上し、子どもたちによりよい形で返ってくるはずです。子どもたちの未来と、それを支える人たちの安心の両方を守る。そのために、医療と福祉の垣根にこだわらず、どんどんと新しい挑戦をしていけたらと思います。